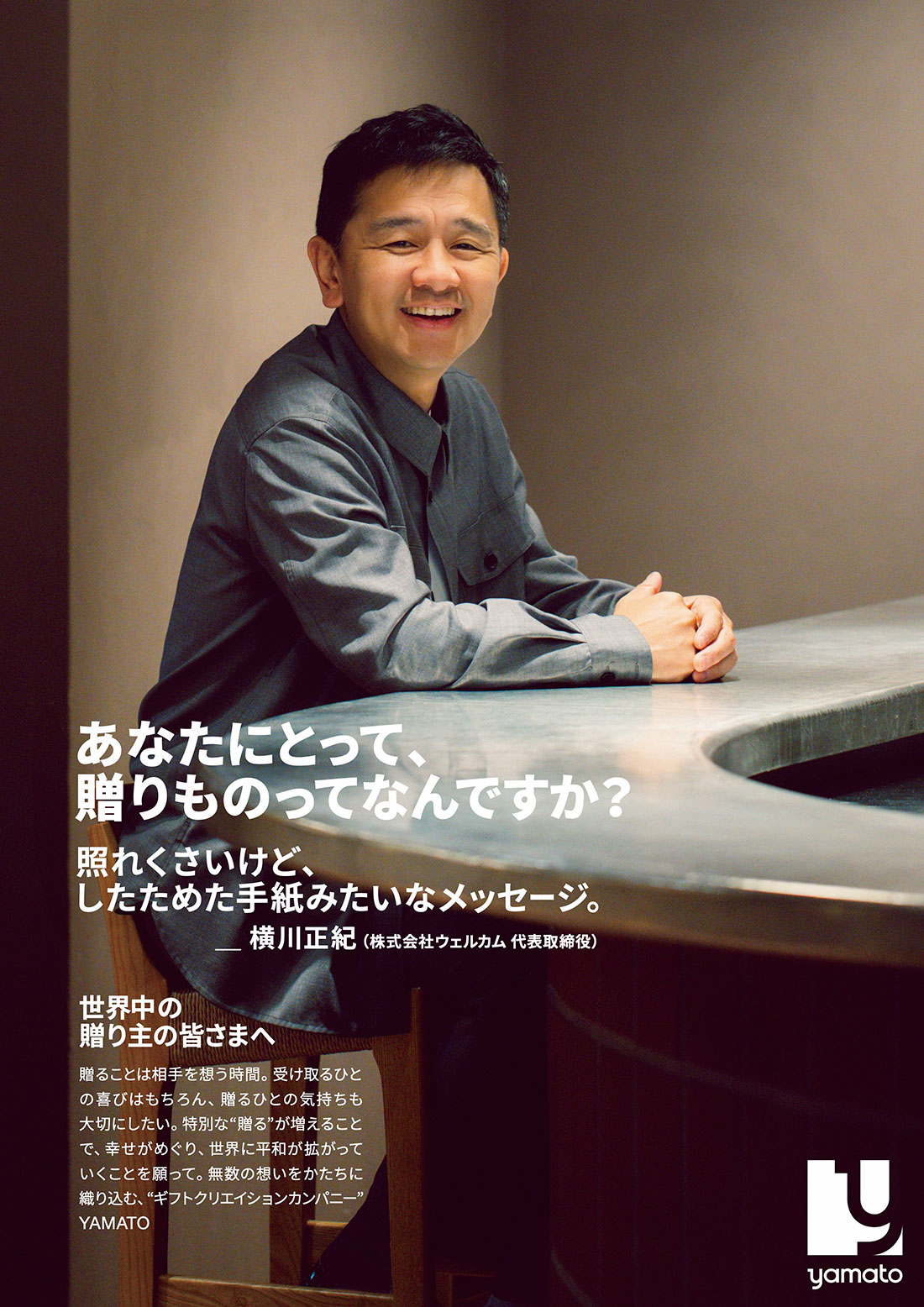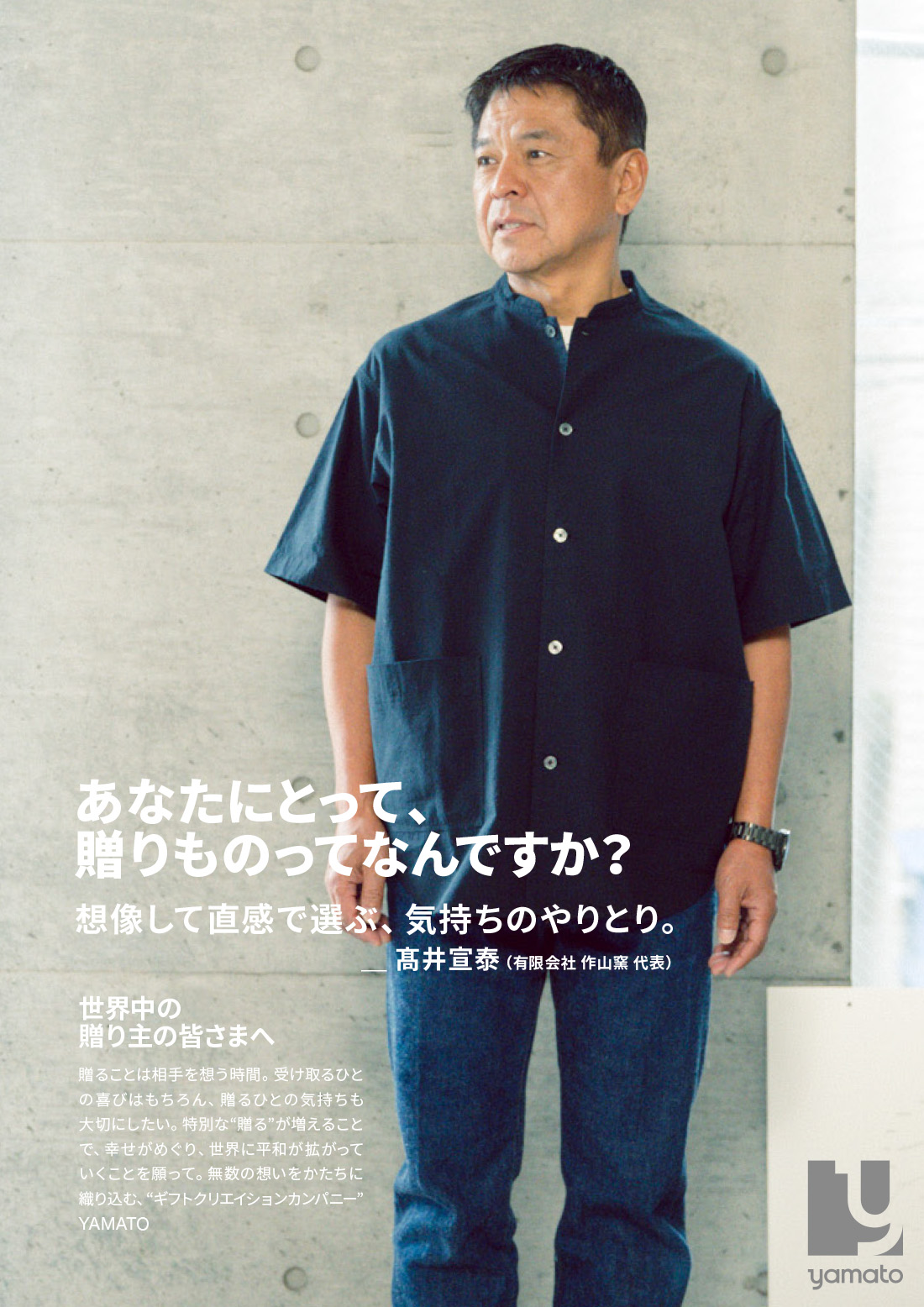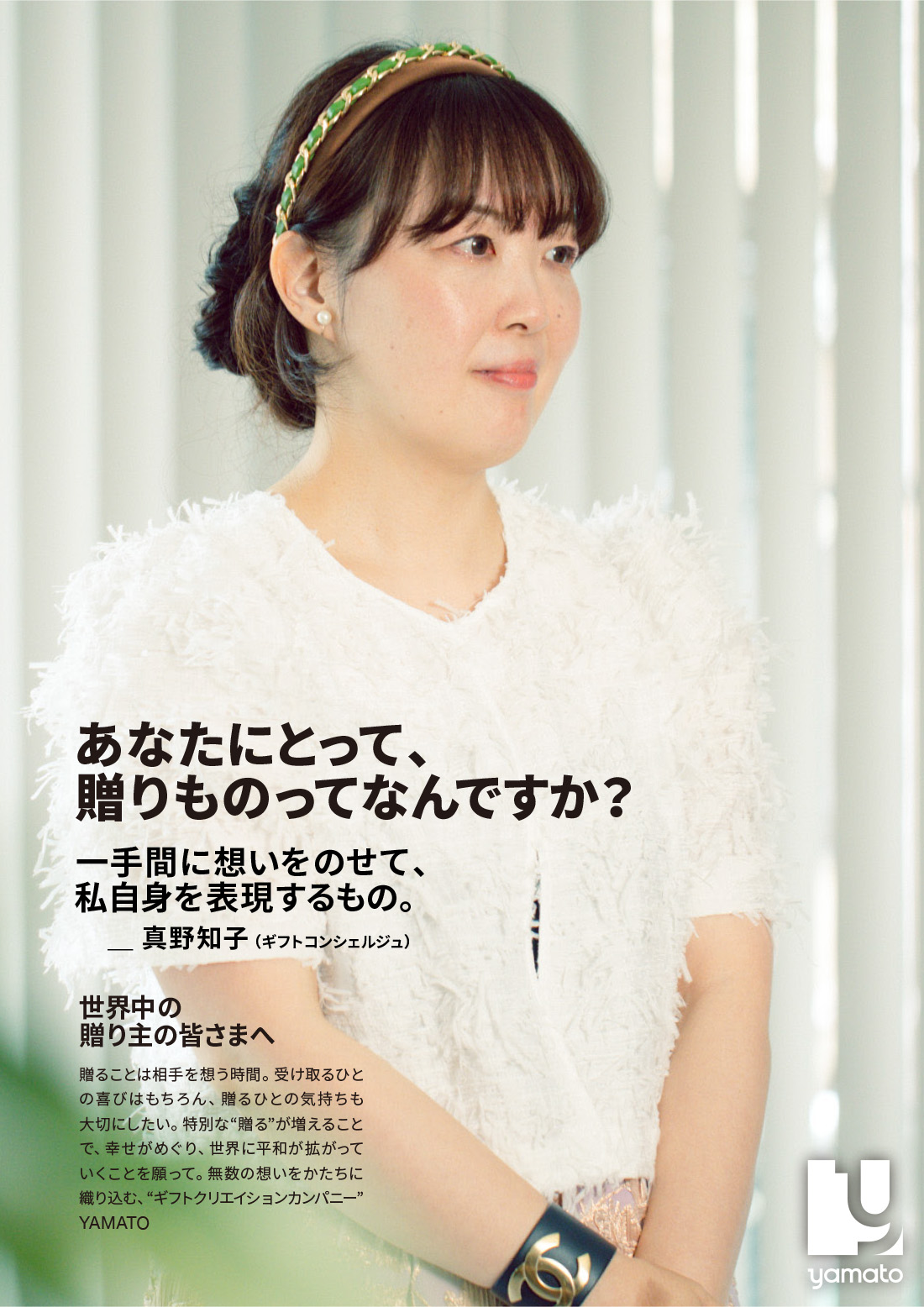YAMATO
YAMATO
あなたにとって
大切にしたい記憶を
記録すること。
GUEST
壱岐ゆかり
さん
(The Little Shop of Flowers 代表)
GUEST
壱岐ゆかり
さん
(The Little Shop of Flowers 代表)
目に見えない そこにあるもの
ギフトを贈るときに最も大切にしていることはどんなことですか?
香りとか季節感は大切にしています。ものを送る時もラッピングをする時に必ずお花を添えます。でも、最も大切にしていることは記憶に残ること、かな。香りでも、視覚的な色合いでも、消えて無くなってしまってもいいんだけど、その人の記憶に残ったらいいなと思って選んでいます。
相手のことを想像して、その人に似合うものを贈るのでしょうか?
その人自身のことを、スーパー想像します。その人が欲しいと思っていることの想像を超えたい。鹿児島のものが来るかなと思ったら札幌が来た、みたいな(笑)。自分が好きなものだと思ったら飼っている犬が好きなもの、とか(笑)。フランスが好きな人だったら、フランスエッセンスを「私が感じるもの」にするとか。その人自身の好きなことやものに、私が想像するエッセンスを追加するんです。そして、できる限り自分の手でラッピングするようにしています。ラッピングするの、大好きなんです。
相手を思いっきり想って、その人の想像を超えていく。素晴らしいですね。壱岐さん自身がこれまでにもらって嬉しかった贈りものはありますか?
全部嬉しかったな。全部…嬉しかった(笑)。ギフトを私のために選んでくれているだけで、すでに充分嬉しいんです。物ももちろん嬉しいけど、「選んでくれた」という事実が嬉しい。その中でも印象に残っているものは、息子が「どうぞ」が言える年齢になった頃に、初めてくれた葉っぱとか石かな。わざわざ教えたわけではないのに、人間って誰かにあげたいと思うんだ、とその行為に感動したことを覚えていますね。特に息子は私とさまざまな産地も訪れているので、自然にたくさん触れています。彼がこの間くれた言葉で嬉しかったのが「ママの仕事は、お花で人を幸せにするんでしょう」って言われたんです。間近でお客さんが受け取っている姿を見ているんですかね? 私はいつも必死でしかないんですけれど。
お花屋さんって過酷なお仕事ですよね、朝早いし、冬は寒いでしょうし。でも、そんな印象を残せているって幸せですね。そのほかにももらったギフトで印象的だったものはありますか?
香りです。香りをもらうタイミングって大抵落ち込んでいたり、疲れていたりする時が多いんですが、香りがついている蝋燭とか、輝いたり揺らぎのあるものだったり、自分のことを思って選んでくれたこの香り、それだけで幸せな気持ちになります。儚いもの、無くなっていくもの、期限があるもの。つまりそれは、見えないし触れないのですが、それを手渡していることにすごく意味があると思うんです。それを感じることができる私たちでいたいと常に思っています。日本人はその見えない「何か」を必ず感じとりますよね。お花だけではなくてそこに添えられている何か。花屋を始めて、そこに気がついたんです。
儚いものや見えないものが持っているものはなんでしょう?
無くなっていくものは尊いんだと思うんです。リトルに通ってくださる人たちは、花と言う形をした目に見えない「想い」を贈りたいんですよね。贈る時は一瞬だけど、その瞬間は特別です。
The Little Shop of Flowersではおもてなしにおいて大切にしていることはありますか?
もう皆できるようになってきたけれど、常に口うるさく言っていた時期もありました(笑)。お花屋さんに来るって、お客さまにとってはとてもハードルが高いことだと思うんです。せっかく来てくれる方に対して「こうです」も言わないし「どうしたいですか?」とも言わない。「AですかBですか」が白か黒かしかない選択肢を渡す問いかけに感じるので、極力しないように、一緒に考えていける接客を心がけています。
そう思っているお花屋さんって増えているんでしょうか?
そうですね、ここ10〜15年で少しずつ変わってきているなと思います。産地から直接仕入れることも多いです。食だけではなくて、花も同じ。土から生まれているもの、という意識や育てている人がいるという感覚。そこに気がついてから、伝えたいという気持ちがより強くなりましたね。
「私じゃなくちゃならない」を 探した先に見つかった 花屋という仕事
なぜお花屋さんを始めようと思ったのですか?
以前、働いていた『IDÉE』を辞めた後、何をしようかなと悩んでいた時期がありました。当時、少しの間携わった広報の仕事で沢山の「手に職を持っている人たち」に触れる機会を得て、彼らの生き方を見ていて、ものづくりする人々を引き立てる立場でいたい、という気持ちが生まれていた時期でもあります。さらに仕事やプライベートにおいて「私じゃなくてもいい」というような出来事が立て続けに起きた時期だったこともあり、「私じゃなくちゃならない」という自分探しをする中で、トライアンドエラーを繰り返しながら、たどり着いた場所が、花屋でした。花を添えることで、ファッションデザイナーさんの展示会のコンセプトをより引き立てることができたり、依頼してくれる方々を引き立てるという活動ができる。右も左も分からない中での挑戦でした。
今回、オランダに旅立つと伺いましたが、この決心にはどんなお気持ちの変化や想いがあるのでしょうか?
5年先の自分が自分の想像範囲外の姿になってたいなあと思ったんです。神宮前で10年間お店をやってきて、あの都会のど真ん中から離れていいとなったら、何がしたいか? 自問自答してみた時の答えが、それでした。あと数年しかできない子育ての時期を後悔ないように寄り添い、そしていろんな初めてを挑戦できるエネルギーが私の中にあるうちにと。後戻りできない、諦めたりできない環境に身を置いてみることで、自分でも想像できない力を自分自身が見てみたいと思っています。もちろんこの東京のお店のチームの理解と応援がなかったら、成し得ないことですし、遠隔地からチームとどう動くことがお互いにとってワクワクすることなのか? を模索したいなと思っています。
壱岐さんにとっての 贈りものとは
今までで一番驚いた贈りものはありますか?
父からもらったお花です。最初で最後の贈りもの。3〜4年前に、父が亡くなる3ヶ月前に、2拠点している山梨の私の家に来た際に、向日葵だけの花束を持ってきてくれたんです。あえて、この花屋の娘に花束を(笑)。多分、私が花屋になったことを喜んでくれたいたんだと思います。自分自身が戻れる家庭を作りきれなかったという無念の気持ちがあった父は、私が「戻れる家を作ってくれた」ということを喜んでくれていたんだと思います。鹿児島男児が花を贈るなんて、想像できないことだったから、それこそ想定を超えてきた出来事でした。
今、考えている贈りものはありますか?
今日、発つ日なので(※取材した日は、壱岐さんがオランダに発つ日でした)、あちらに落ち着いて少し時間ができたら、コーヒーを飲みながら、お世話になった近い人たちに手紙を書きたいと思っています。レターセットはもう準備してあります。手紙、好きなんですよね。言葉を短くまとめるのが苦手なんですが、でもそれでいいと思ってて。つらつら、想いを巡らせながら書き連ねる文章って心惹かれるんです。経緯や理由や思考の過程が見えるもの。2と3があったから今がある、みたいな。2と3も正解だし、大切って思うから、そんな文章を書いて贈りたいですね。書き終えた時に、どんな気持ちになるんだろうな。この10年間ってこうだったなって、きっと手紙を書きながら内観できるだろうなと、今から楽しみです。多分、それを経たら、この先の未来が少し見えてくるかな。
日常の中に「余白」なんて、本当になかった忙しい日々でしたよね
そうですね。日本語の話になりますが、「私」っていう漢字は「和多志」と書く語源を持っているそうなんですね。森羅万象じゃないけれど、日本人は植物や自然や生き物と一緒に生きているという感覚を持つ民族なんですって。「私」という「我」ではなくて、「和多志」として自分が暮らすこと。「みんな」でしたいこと。「みんなと一緒にやりたいこと」ということを考える感覚が、もともと私たちが持っていた感覚なんだと思うんです。今は「個性」はあるのか?と叫ばれますが、「自分」ということを取り立てて意識することより、全体を考えていたいという気持ちが強くなりました。毎日もちろん慌ただしいし、余白はないけれど、この全ての日々や現象は、私自身そのものだし、だからもう「余白がない」と思わなくなったんです。
最後の質問です。壱岐さんにとっての贈りものってなんでしょうか?
「記憶を記録すること」かな。記すこと、脳裏に残ることって、とっても大事なことだと思います。特にこの時代においては、日々のスピードが早すぎて、気持ちも感覚もあっという間に過ぎ去ってしまう。大切にしたい「今生きている理由」みたいなものが残したい。日々の暮らしの中で残せることは「贈る」ということを通したら、とても色濃く残しやすい。本当は日々の暮らしの中で、出汁の味も、自然が織りなす音も、花や料理の香りも、それ以外のいろんな感覚も記憶に残っているんです。それを忘れてはいけないし、そこにそれがあったという証をちゃんと残していかないと、大事なものが未来に残せないと強く感じています。法律にしたほうがいいくらい、大切にしたいことです。
目に見えない贈るひとの「想い」を、花という形で彩りを添えて届ける素晴らしいお仕事と生き方のお話でした。ありがとうございました。
PROFILE
The Little Shop of Flowers 代表
壱岐ゆかり
インテリアデザインとPRの分野でキャリアをスタートさせた後、2010年に代々木上原に週末だけの花屋THE LITTLE SHOP OF FLOWERSをオープン(現在は祐天寺と渋谷に2店舗を構える)。日本の和花の静かな気品と西洋の花々を織り交ぜた表現で、フラワーデザイン、スタイリング、ワークショップなど、多岐にわたって活動中。役目を終えた花々を染料として再生し、日常に詩的な贈りものとして届ける同店オリジナルギフトラインにも取り組む。